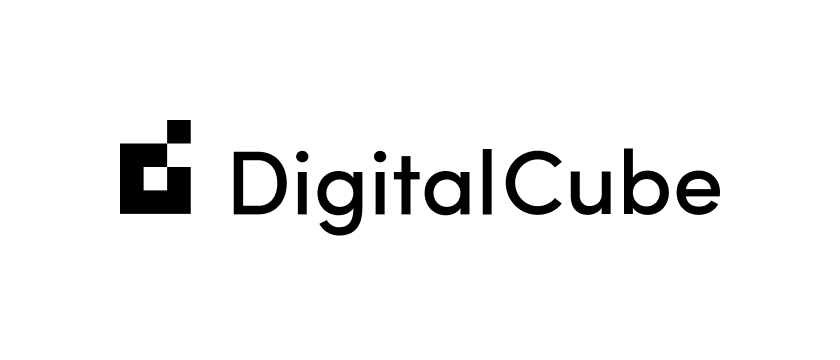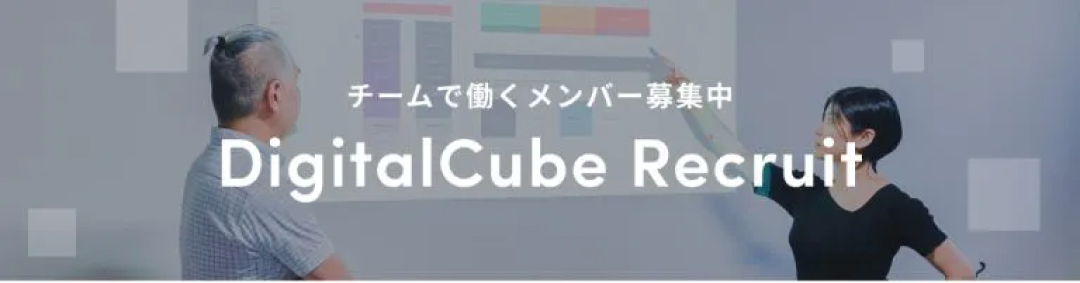DigitalCube BizDev の岡本(秀)です。先日開催された「JP_Stripes 東京 vol.24 オンラインビジネスの収益化を始める、改善する、支援する」にてパネルディスカッションへの参加機会をいただきました。今回の記事では、このイベントでどんな学びがあったかなどを紹介したいと思います。
イベントについて
このイベントは2025年4月9日(水)にサイオステクノロジー株式会社で開催され、「オンラインビジネスで収益を上げるうえでの始めかたから改善方法、そしてそれらを支援する方法」をテーマに、具体的な事例をもとにした発表とディスカッションが行われました。今回は、SaaSビジネスにおけるStripeの活用について、立ち上げ、改善、支援という3つの異なるステージからの知見が共有されました。
2つの事例から、Stripeの立ち上げと改善について学ぶ
イベントはまずStripeをサービスに導入されている2社の事例セッションから始まりました。それぞれのセッションはStripe活用における「立ち上げ」と「改善」という2つの切り口から体験や運用のポイントについて紹介されていました。
【始める】ClipCrow – 一人会社のSaaS開発とStripe活用事例
最初のセッションでは、栗原さんからClipCrowというSaaSサービスの開発と運用、特にStripeを活用した課金システムについての発表がありました。
栗原さんは業界歴約30年のベテランで、2020年にクリップクロウという一人会社を設立。基本的に外部リソース(オフショア開発)を活用しながら、SIコンサルティング収益を原資として独自SaaS事業を立ち上げてきたとのことです。
特に印象的だったのは、栗原さんのビジネス構築アプローチです。
- 段階的な資金調達: 初期はSI案件で収益を確保しながら製品開発を進め、3年かけて製品ローンチにたどり着いた
- Stripeによる課金モデル: フリーミアムモデルで5シートまで無料、追加シートは権限レベルに応じて1000円または500円/月の価格設定
- Stripeの機能フル活用: 決済UI、日割り計算、領収書発行、多通貨対応など、できる限り課金関連機能をStripeに寄せている
ClipCrowはカード型データベースを基盤としたタスク管理ツールですが、複数のテナントを切り替える設計は、医療従事者など複数施設で働く人をターゲットに考えられたものだそうです。Slackの課金モデルをベンチマークにしているというのも興味深い点でした。
価格設定の考え方も参考になりました。同種のサービスがアメリカでは1500円程度/ユーザーなのに対し、日本の経済状況を考慮して500〜1000円の価格帯に設定。「日本向けに値段を設定しないと売れない」という現実的な視点と、「国際化して世界でも売れるように」という拡張性の両立を目指しているとのことです。
栗原さんが「1億円ほど投資して開発した」と語っていたのは、一人会社としてはかなり大きな投資に思えました。こうした長期的な視野を持った開発スタイルは、私たちがSaaS支援を行う上でも大いに参考になります。
【改善する】ソースネクストによる不正対策事例
続いて、ソースネクスト株式会社の金巻さんから不正対策についての事例発表がありました。
ソースネクストさんは、元々PCソフトを販売する会社から始まり、現在はAI搭載IoT製品(ポケトークなど)をメインに展開されています。年間50億円の売上があるECサイトを約20年運営してきたそうですが、長年の使用で内部的に複雑化し、運用保守コストの増大や業務の生産性低下などの課題が生じていたとのこと。そこで2020年からシステム刷新を進め、新システムでStripeを活用されています。
特に興味深かったのは、Stripe Radarを活用した不正対策についての知見です。
- 不正の発生状況を定期的に監視し、月1回のペースでルールの見直しを実施
- 過去数カ月間で1回も引っかからないルールは削除するなど、ルールの整理も重要
- Stripe側で判定されるリスクスコアをどの程度でブロックするかを自社で設定
- メタデータを活用して独自の判定ルールを追加
金巻さんの「不正対策は設定して終わりではない」という言葉が印象的でした。新商品やサービスによって狙われる条件が変わり、不正手段も日々進化するため、定期的な監視やチューニングが必須とのことです。これは私がStripeにいた頃によく耳にした課題でもあります。多くの事業者が不正対策を設定した後に放置してしまい、後々問題が発生するケースを見てきました。
また、Q&Aセッションでは「領収書や決済金額の処理をもっとStripe側に任せられると知っていれば良かった」という気づきも共有されていました。これも私がStripeにいた頃によく耳にした課題です。最初からStripeの機能をフル活用する設計にすれば、後々の運用が楽になります。
【支援する】パネルディスカッション「Stripe構築支援の最新動向」
最後に、私(岡本)、Instollの友田さん、サイオステクノロジーの小濱さんによるパネルディスカッションが行われました。異なる立場からStripeの構築支援に関わる私たちが、経験や知見を共有しました。
よくある相談内容
私からは、2025年3月までの3年間StripeのDeveloper Advocateとして活動していた時の経験を元に、「ベストプラクティスを知りたい」という相談が多かったことをお話ししました。Stripeのドキュメントは非常に充実していますが、どのページを読めば今抱えている課題を解決できるかのような発見フェーズの難易度が少し高めです。そのため、お客様の要件を聞いて適切な機能やAPIを紹介する「翻訳者」のような役割が求められていたと認識していました。
友田さんからは、SaaSを作った後で決済を後付けしたいケースや、SaaSを作りたいが決済をどうすればいいか迷っているケースが多いとのお話がありました。「Stripeのドキュメントを読んだが分からない」という相談が多いという点は、私の経験と共通していたかと思います。
小濱さんからは、相談の7〜8割がSaaS事業者からで、PDFなどで手作業だった請求業務を自動化したいケースと、新規SaaSビジネスの立ち上げでバックオフィス業務をStripeに任せたいケースが半々という話がありました。
導入ステージ別の課題
導入ステージ別の課題については、特に設計段階の重要性を強調させていただきました。どの機能をフリーミアムにし、何を課金対象にするか、テナント構成などを後から変更するのは非常に困難です。クリップクロウの栗原さんの事例は、この点でも参考になりました。初期設計でSlackのようなテナント切替と課金モデルを設計し、Stripeの機能をフル活用する方針を明確にされていました。
また、運用時の課題として、開発リソースが他プロジェクトに移り、維持管理が手薄になりがちな点を議論しました。私自身、DigitalCubeからStripeに転職した際、3Dセキュアの対応で苦労していた旧同僚の姿を見ていました。この経験から、エンジニアにStripeダッシュボードを定期的に見てもらう習慣づけの重要性をお話ししました。
将来のトレンド
将来のトレンドとして特に注目したいのは、代理店モデルの自動化とStripe Connectの活用です。小濱さんから、代理店を持つSaaS事業者からの相談が増えているという話がありました。現状はアナログで処理している収益配分をStripe Connectで自動化できる可能性があります。
これは栗原さんのQ&Aでも触れられていた、エンタープライズサポートの追加課金モデルや代理店システムの構想とも重なる部分があります。個人運営のSaaSから、より大規模なビジネスへと発展させるための重要なポイントになりそうです。
友田さんからはアフィリエイト・リファラル機能の自社構築についての話題もありました。法規制の観点から慎重に検討する必要がありますが、ビジネス拡大のための重要な選択肢になり得ます。
また、イベントに参加されていたStripeの佐々木さんからは「Connect 2.0」と呼ばれる進化したStripe Connectについての情報共有がありました。リスクをStripeに渡したまま、プラットフォーム側の柔軟性が増している点が特徴とのことです。
イベントからの学び – 異なるステージのStripe活用法
今回のイベントでは、Stripeを活用したビジネス構築のさまざまな側面について議論できました。特に印象的だったのは、各発表者が異なる開発ステージや企業規模でStripeを活用している点です。
立ち上げステージでは、クリップクロウの事例から一人会社がStripeを活用して国内外に展開可能なSaaSを構築する方法を学びました。成熟ステージでは、ソースネクストの事例から大規模ECサイトのリニューアルでStripeを導入し、高度な不正対策を実現する方法が示されました。そして支援の視点からは、パネルディスカッションを通じて様々な企業の実装・運用をサポートする立場からの知見が共有されました。
特に栗原さんのアプローチは、小規模から始めるSaaS開発のモデルケースとして参考になりました。SI収益を元手に独自プロダクトを開発し、出来上がった製品を持って資金調達に臨むという戦略は、リスクを抑えつつ自社プロダクトを生み出す一つの方法だと感じます。
また、SaaSの課金設計において、日本市場の特性に合わせた価格設定を考慮しつつも、Stripeの多通貨対応を活かして国際展開の可能性を残すという考え方も勉強になりました。
まとめ
今回のイベントで得た知見を、私自身のSaaS開発支援にも活かしていきたいと考えています。特に設計段階からStripeをフル活用することで得られる恩恵を、事前に開発・事業者両方がどれだけ知っているかは、今回のケースでもあったように、後から生まれる困ったを大きく減らせる可能性があります。また、もしそれが難しくとも、不正対策やサブスクリプションのMRRや解約率など、運用方面での継続的なサポートという形で顧客や企業の収益モデルに貢献できるではないでしょうか。
また、友田さんが提案していたビジネスモデル別の統計データやベストプラクティスの共有は、SaaS事業者にとって非常に価値のある情報だと思います。私たちSaaS支援者が実践例や知見を集約して共有していくことで、日本のSaaS事業の成長に貢献できるのではないかと感じました。
Stripe を活用したオンライン決済システム導入をサポートします
株式会社デジタルキューブは Stripe 公式パートナーとして、自社サービス開発で培った経験を活かし、Stripe を用いた決済システムの導入を支援します。多言語対応の決済フォーム実装、モバイル支払い対応、柔軟な従量課金システム構築など、ユースケースに合わせた活用方法の提案から、専用ダッシュボードの開発まで幅広くサポートします。
SaaS ダッシュボード開発や EC サイトへの Stripe 決済導入など、様々な導入実績があります。 API の呼び出しだけで決済機能を実装できる Stripe の利点を最大限に活かしたシステム構築をお手伝いします。